ご利用規約 | プライバシーポリシー | サイトマップ
在宅ホスピスについて
在宅ホスピスケアとは、治療目的ではなく症状緩和などを目的とした全人的ケアをご自宅にて実施することです。現在では在宅緩和ケアと呼ばれることも多く、主に末期がんの患者さんなどを対象としています。
緩和ケア(ホスピスケア※以降「緩和ケア」と表記します)では、「最期までその人らしく生きる」ことが目標となります。この緩和ケアを在宅で行う場合、患者さんご本人とご家族が「自宅で最期の時を迎えたい」と望んでいることが原則となります。

在宅緩和ケアでは、基本的にご自宅で患者さんを看取ることになります。また、患者さんの肉体的苦痛はもちろん、心理的、社会的な苦痛などを和らげるケアが行われます。そのため、患者さんと暮らすご家族も「緩和ケア」とはどういうものかを知っておく必要があります。
※HIV(エイズ)の末期の患者さんも緩和ケアの対象ですが、症例的にはがんの患者さんが圧倒的であり、在宅でHIVの患者さんの受け入れ体制を整えている医療機関はほとんどないと思われます。
緩和ケアとは…?
【緩和ケアの定義】
緩和ケアとは、生命を脅かすような状況に直面している患者さんとそのご家族に対して、生活の質(QOL=クオリティ・オブ・ライフ)を向上させるアプローチのことです。
疾患の痛みなどの身体的症状、心理的、社会的、スピリチュアルな問題に関する苦痛の軽減や予防を図ります。
緩和ケアではこれらを疾患の早期から最期の時まで、さらにはご遺族の悲嘆(グリーフケア)に対してもサポートしていきます。
 緩和ケアの指針
緩和ケアの指針
- 痛みや吐き気などの苦痛な症状から解放します。
- 生命を尊重し、自然な過程のなかでの死を認めます。
- 死を早めたり、引き延ばしたりしません。
- 患者さんの心理的なケアや、スピリチュアルケアを合わせて行います。
- 患者さんが死を迎えるまで、人生を積極的に生きてゆけるように支えます。
- 患者さんが病気で苦しんでいる間から、死別した後まで、ご家族がその後の生活に適応できるように、またその悲嘆に対してもサポートしていきます。

- 患者さんやご家族に対するケアをチームアプローチを用いて実施します。(※死別後のカウンセリングを含む)
- QOLを高めて、病気の経過に良い影響をもたらすようにします。
- 病気の初期の段階にも適用します。延命を目的とする化学療法や放射線療法などとも連動して実施することも可能とします。また、患者さんに苦痛を与える合併症などの対処法や検査、研究などにも適用されます。★
WHO(世界保健機関)2002年より
★以前の緩和ケアの定義(WHO1990年)では、「治癒不能な状態の患者さんとその家族」を対象としていました。しかし、2002年の定義によって病気の初期の段階でも緩和ケアが受けられることになりました。
日本においても2006年に成立した「がん対策基本法」で、疾患の早期から緩和ケアを提供する体制を整えることと明記されています。また、2008年の「診療報酬」の改定において緩和ケアの対象は、それまでの「末期の悪性腫瘍」から「末期」の言葉が削除されました。
これらのことから、緩和ケアの対象は「病気が治る、治らない」に限らず、その「病気の症状を緩和する」ために実施されるべきであるといえます。
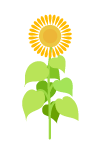
実際に、末期がんではない患者さんが外来などで症状コントロールを行いながら、化学療法などの治療を平行して行っているケースもあります。
しかし、緩和ケアを専門とする入院施設が少ないため実際に入院する患者さんのほとんどは、やはり末期がんの方です。さらに、末期がんの患者さんであっても、ベッドが空かないため、入院を待っている「待機患者」さんが大勢います。
これらのことから、今後、在宅緩和ケアの需要はますます高まっていくことが考えられます。
在宅緩和ケアの流れ
在宅緩和ケアを行う一般的な流れはおおよそ以下の通りです。
ここで示すケアの流れは、在宅での「看取り」を前提とした「ターミナルケア」と考えてください。
WHOが定義する、疾患初期からの症状緩和を目的とした緩和ケアは、在宅ではあまり実施されません。なぜならば、在宅医療の原則が「通院困難」な患者さんが対象だからです。
がんの初期段階では、外来または入院で治療を行うケースが多いと考えられます。
※ターミナルケア…がんの末期において、死の直前の時期を「終末期」もしくは「ターミナルステージ」と呼びます。看取りも含めたこの時期のケアを特にそう呼びます。
 在宅緩和ケア開始の相談
在宅緩和ケア開始の相談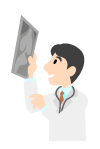
- 在宅医療を依頼する医療機関に連絡します。専門の相談員が電話などで応対するケースや、外来にて受診し、医師と相談します。
- 医師は、患者さんやご家族の希望を聞き、また職場や家庭環境なども考慮して治療方針を考えます。
- 患者さんによっては、在宅での緩和ケアが難しい場合もありますので、病院などの施設に入院している場合は、退院前に相談したほうがよいでしょう。また、入院中の場合は主治医に診療情報(いわゆる紹介状)を提供してもらうとよいでしょう。
【在宅緩和ケアを実施するための条件】
一般的に在宅で緩和ケアを受ける際には、いくつかの条件があります。
- 患者さんもご家族も、ご自宅でのターミナルケアを望んでいて、看取るご家族がいること(複数いることが望ましい)。
- 患者さんご自身が末期であることを知っていること(認知症などの場合は例外)。
- 在宅ケアを開始する段階で、症状のコントロールがひととおりできており、そのコントロールが容易であること。
- 医療者(在宅ケアを行う医師と、それをサポートする訪問看護ステーション)と患者さん宅の距離が近いこと。
- 患者さんもご家族も積極的な延命治療を希望しないこと(延命治療を望むのであれば、病院等の施設のほうがよい)。
上記のすべてを満たしていなければ、在宅緩和ケアが受けられないということはありませんが、最初の2項目が満たされていない場合、在宅緩和ケアは非常に難しいでしょう。
また上記以外にも、望ましい条件はいくつかありますが、受け入れる医療機関などによっても異なりますので、医療機関の方までご相談ください。
 在宅緩和ケアの開始
在宅緩和ケアの開始- 医師は緩和ケアチームを整えます。訪問看護ステーションや薬剤師、管理栄養士、ケアマネジャーなどと連携をとり、患者さんのケアにあたります。
- 緩和ケアでは、ご家族もまた患者さんとともにケアの対象となります。緩和ケアチームでは、時にはご家族の心理的サポートも実施します。
- しかし、ご家族はケアの対象であると同時に、緩和ケアチームの一員でもあります。患者さんのことをよく知るご家族が中心となって患者さんをケアしていきます。
- ※ホスピスケアは元来、欧米の思想に基づくものですが、宗教観や文化が大きく異なる日本に、そのまま欧米型のホスピスケアを取り入れることは困難です。
- 日本型の在宅緩和ケアの大きな特徴は、ご家族が中心となって患者さんを看取り、医療者はその援助者であるということです。
- 患者さんをケアする環境においても、医療者や介護サービスだけでは不十分であり、ご家族の介護力が必要となります。
- しかしそれ以上に、ご家族が思い残すことなく患者さんのケアを尽くし、最後の貴重な時間を共有することで、患者さんが亡くなった後でも、かけがえのない宝として残るのです。
 在宅緩和ケアの安定期
在宅緩和ケアの安定期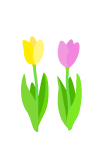 患者さんの状態が比較的安定し(しかし、ゆっくりと確実に状態は悪くなっていきます)、ご家族も介護に少しずつ慣れてくる時期です。
患者さんの状態が比較的安定し(しかし、ゆっくりと確実に状態は悪くなっていきます)、ご家族も介護に少しずつ慣れてくる時期です。- この期間が、患者さんとご家族がかけがえのない思い出を残す大切な時間になります。
- 医師による訪問診療は週2~3回ですが、医師や看護師などと電話などで連絡を取り合い、急変などに備えます。
 ターミナル期
ターミナル期- 患者さんの症状は急速に悪化し、症状コントロールも難しくなります。患者さんの苦痛があまりにもひどい場合には、在宅にこだわらず入院を勧められるケースもあります。
- 医師や看護師は連日訪問し、24時間いつでも往診できる体制をとります。また、ご家族は看取りの準備を進めます(ご家族が実施するご遺体の清拭などの死後の処置などで、緩和ケアチームが指導します。これを「デスエデュケーション」と呼びます)。
 在宅緩和ケアの期間
在宅緩和ケアの期間
患者さんの状態や症状の変化などで個人差がありますので、一概には言えません。在宅緩和ケアを開始した直後にお亡くなりになる患者さんもいれば、1年以上ご自宅で過ごされる方もいます。
参考としては、在宅緩和ケアを専門としている診療所では、在宅ケアの開始から看取りまでの平均は3週間~1ヵ月 だそうです。
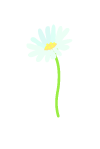
※末期がんの定義…厳密な定義はありません。がんの治療を諦めたときと過程した場合、3~6ヵ月以内にお亡くなりになるケースが多いとされています。しかし、どこで「助かる見込みがない」と判断するかは医療者でもとても難しいとのことです。
治すための治療を続けるか、ターミナル期へ備えるケアに切り替えるかの最終的な決断を下すのは、患者さんとそのご家族です。
治すための化学療法や放射線療法は、患者さんに苦痛をもたらします。決断を下す時期を見極めることは、医療者ではない患者さんやご家族にはほぼ不可能であると思われます。
とても大きな決断になりますので、主治医以外の別の医師の見解を聞き、複数の視点から判断すること(セカンド・オピニオン)をお勧めします。



 このページのトップへ
このページのトップへ